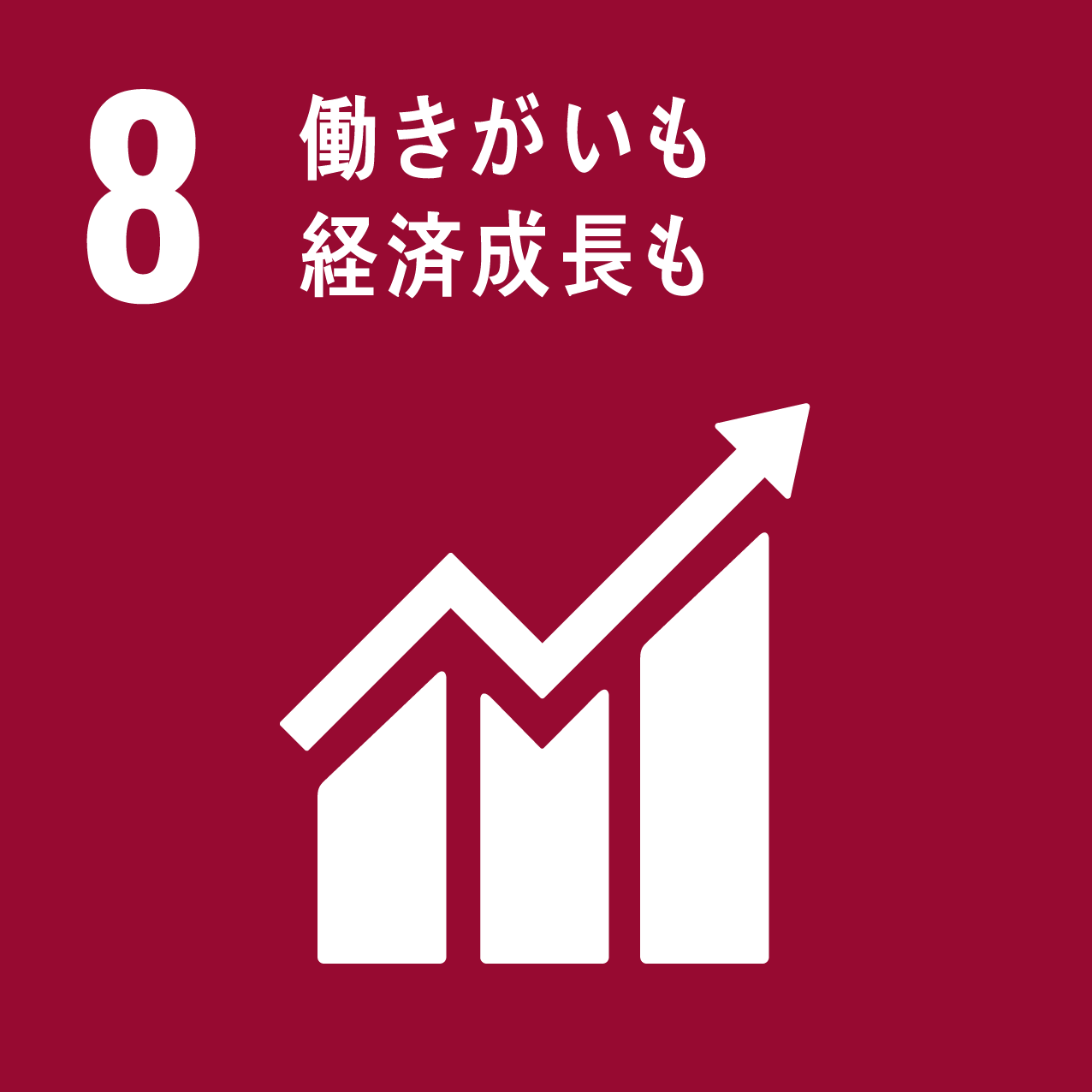広報活動
シリーズ③ウッドデザインで未来をつくるリアルストーリー 「木」のデザインのチカラで林業と福祉の活性化を目指した「林業×福祉連携プロジェクト『森tebaco』」

「これが間違いなく一等賞だ!と思って選びました。」
2023年ウッドデザイン賞受賞記念セミナーで審査委員のプロダクトデザイナー 増田文和氏が冒頭で発した「森tebaco」の評価です。
「森tebaco」は2023年度ウッドデザイン賞最優秀賞である農林水産大臣賞を受賞しました。パワープレイス株式会社、社会福祉法人 幸仁会 川本園、NPO法人 木育・木づかいネットの3者が共同で受賞していますが、このうち川本園は障がい者の方々が働く就労支援施設です。
スケールの大きい木造建築やプロジェクトの受賞作品が多い中、このコロンとした手で包みたくなるような『森tebaco』がなぜ最優秀賞を受賞したのか、審査員をうならせた背景についてお話をお伺いしました。
林業・木材のデザインで障がい者の生き生きと活躍する場を創出する
プロジェクト名にもある林業×福祉連携プロジェクトとは、令和4年度林野庁補助事業のひとつ「林福連携で行う優れた地域材製品開発」についての公募で、福祉関係者と、林業木材産業者、デザイナー等が連携して、地域材を活用した木製品を開発し、地域振興のモデルとなるような取組を行うことです。

深谷市にある社会福祉法人幸仁会川本園。広い製材所では忙しそうに利用者さんたちが働いていました。
このプロジェクトに参加している福祉法人幸仁会 川本園は埼玉県深谷市にある就労継続支援B型事業所で、全国では珍しい木材の加工機や自動カンナなど、一般の製材所やプロの大工が使う設備と仕事場の環境が整えられています。

丁寧に地域産材で作られた製品が積み上げられている。
川本園を訪れてみると、丸太や製材された木材が積まれた山に、建物からは製材機の音。建物に一歩入ると高性能加工装置がありそれを操作していたり、別の部屋では電動のこぎりや自動カンナで次々と木材を仕上げていく光景が見られました。
「ここでは作業の上手なものに合わせて作業をしてもらいます。正確にできる人にペースを合わせて工程をこなすことで、全体を引っ張ってクオリティが上がります。自分が以前働いていたところでは、作業に慣れてない人に合わせていましたが、優しくしていることは逆の結果になってしまうと思います。」と話すのは社会福祉法人 幸仁会の田中初男理事長。
製材・乾燥・仕上げという製材の工程を全て行い、加工品も作る。40人いる利用者全員が程度に合わせ、作業することができる、さながら自動車部品工場のような仕組みだと言います。
「職員がいなくても動くような仕組みを作ってます。工程ができる、できないは彼らの能力を見抜けていない我々職員の責任。それでも合う仕事が見つからない時は、われわれ職員が一生懸命に仕事を作るとか、何かを見つけてあげなければいけない。それが職員の仕事だし職員の評価だと思う。」

作業は、作業が早い人から学びスキルを上げる。
以前は竹加工品製品などを作っていた同施設だが思ったように需要が伸びず、県からの紹介で埼玉中央部森林組合から地元の埼玉材を仕入れ製材作業をするようになりました。
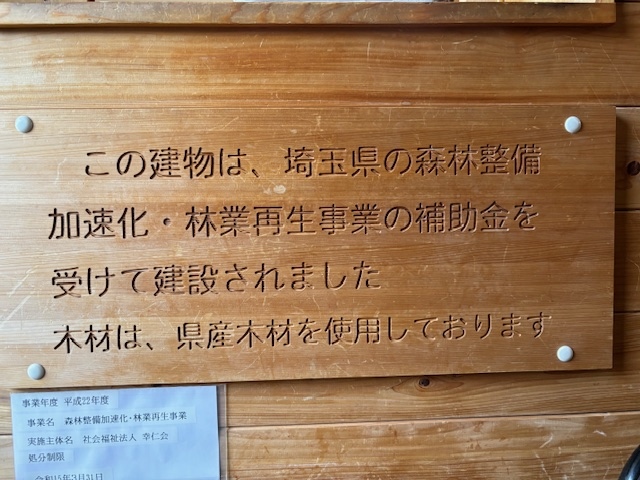
木造の作業所。県産材を使用している。
福祉事業としては、県や行政、福祉団体や企業のイベントの記念品などの木製品つくりが多数だが、川本園では幼稚園や保育園、児童館などのイスやテーブル、棚、プランターなど大きな製品も制作しています。
福祉施設が林業を支援する
ノベルティとして売れるための「上」を目指したものづくり。一番苦手だったのがデザインでした。

製材から製造まで一貫して製品を管理できる。
2年前、職員をはじめとしたウッドワークのメンバーで商品開発委員会をつくったものの、業務が多忙でなかなかうまくいかなかったそうです。
そのような中、障がい者自立支援に取り組む認定NPO法人日本ヘルプセンターから林野庁の補助事業で、福祉施設が地域産材を活用し、一般消費者に向けた魅力的な付加価値の高い製品を開発するために木工を行う福祉作業所がないかと打診があったのが取り組みのきっかけでした。
「親交のあったNPO法人木育・木づかいネットの浅田茂裕年生から林福連連携の話があり、プロダクト商品が開発できると思い、取り組むことにした。」
田中理事長は「林業×福祉連携プロジェクト『森tebaco』」のプロジェクトの始まりについてこのように話しています。

社会福祉法人幸仁会 田中理事長。
得意を活かせるモノづくりを「魅力ある地域材製品の新たなデザインを創出すること」
『森tebaco』プロジェクトはNPO法人木育・木づかいネットが共同事務局を担い、内田洋行グループのパワープレイス、グラム・デザイン、埼玉大学、埼玉県中央部森林組合など連携、令和3年度より取り組んでいるプロジェクトです。
川本園が課題としていた企画やデザインについてお話を伺いました。

プロジェクトメンバー。
ーまず、このプロジェクトのきっかけは?
NPO法人木育・木づかいネット 多田知子さん(以下多田さん):埼玉大学の浅田先生と前理事長時代から懇意にしている川本園の田中理事長の悩みとして、福祉作業所の持つ課題やデザイン力の弱さや作れるものが限られているという問題を相談されたところからです。
ちょうど令和3年度に林福連携が立ち上がるという事になって、日本全国で対応できる高い技術力をもっている作業所は川本園さんしかないという事で、川本園さんにお話をもっていって始まった話でした。

NPO法人木育・木づかいネット 多田知子さん
ープロジェクトを進めるにあたってどのような課題に向き合いましたか?
株式会社内田洋行・山田聖士さん(以下 山田さん):アイデア出しをするときに何ができるのか、川本園の木工所でないので作れるものは何だろうと具体的に提案しました。
今までやってきたアイテムをブラッシュアップして提案し、最終的にこれが向いているとなりました。
ー『森tebaco』の由来は?
奥さん:大切なものを入れる箱という意味で、もう一人のキーパーソンのグラム・デザインの赤池円さんが名付け親ですね。方向性やアイデアを出してくれ、重要なポイントを提示してくれて私たちの話を支えてくれましたね。

パワープレイス株式会社 奥 ひろ子さん
ーいい名前ですね。覚えやすいですし。
多田さん:イラストも季節ごとに入れようとか、そういうアイデア出しもありがたかった。
ー森tebacoは何種類商品がありますか?
奥さん:3種類です。フレームタイプと時計があり、フレームもカレンダーと季節の絵があります。時計が色違いで2種類あります。
ーフレームの中の絵もいいですね。
パワープレイス株式会社 森 麻衣子さん(以下森さん):木にデザインを添える、という気持ちで描くのと、かつ、この『森tebaco』の世界観をどう表現できるかと考えました。

パワープレイス デザイナー 森 麻衣子さん
ープロジェクトの自走化はお考えですか?
多田さん:計画自体は3か年で考えていて、1年目で企画立案、2年目でブランディング評価、3年目以降はブランドの忠実化と職場つくりと考えていて、ある程度沿って進行しています。
今後は自走化するために企業をコラボレーションをしたり、そのための開拓の期間に使用と考えています。
仕組みが出来てある程度世に出れば、川本園さんが企業とやり取りして取り組みが世に出るという励みになると思います。

これからの展望を語るプロジェクトメンバー。
「障がい者にとって魅力ある職場をつくること」
「福祉事業の小物類には限界がある。丁寧にゆっくり心を込めて作るだけではなく、きれいに早く作れるものでなくてはいけない。福祉の工賃はどうしていますか?とよく質問されます。できただけ点数にして払うのが一般的ですが、ここでは月額500円を全員に払っています。そのためにはきちんとした単価で買ってもらえる、結果のでるものを作業にしなくてはいけません。」
幸仁会の田中理事長はそう話します。

今後、障がい者の出生率も減り、事業所に通う利用者も減っていくことを考えると、今の力を持続するために守りに入る時期になったといいます。
「利用者さんはいつも一定ではありません。大量注文が受け入れられるわけでもありません。前に小売りもやっていましたが、売れなくてやめています。小物はどちらかというと作品という感覚で、商品ではないのです。」
『森tebaco』も最初の試作段階ではパートも多く、仕上げるまで時間がかかり難しかったと職員の野辺香織さんは語ります。

デザイン性を追求すると売るために人件費などがかかりすぎ、販売価格が高くなってしまう、難しい作業が入ると数量が作れない、福祉事業所にとって永遠の課題だといいます。
しかし、今回この林福連携のプロジェクトに関わり、今まで思いつきで作っていたが、モノを作る順序や仕組みを学べたといいます。
野辺さんは「今回パワープレイスさんや赤池さんが関わってくれたことで、諦めないことを学べました。難しいけど両者に出来ないこともまた組み立て直して自分たちで解消し、この『森tebaco』という形になったこと、それが一番大きな成果です。」と語ります。

プロジェクト事務局の多田さんは、実際作ってみて原価の問題やロイヤリティー管理など仕組み作りが必要だと語ります。
「注文をたくさんとれればいいというかとそうでもないのが福祉作業所。例えば川本園さんが大きな受注を取れたら他の事業所に出せるような商品開発をしていけばいい。そういう仕組みをわかって福祉事業所さんにちゃんと興味を持ってもらえる企業と繋がっていきたい。」といいます。

色々な事業者がつくれるように細かい作業を省き、作業する人に危険がなく得意を活かせるものにする。大量生産ではなく記念品とか受注発注のような製品を生み出し、なにより川本園の製品つくりの良さを一般に知ってもらい手に取ってもらう。
福祉作業所が自走するためには、林福連携の仕組みを利用した適切な商品を受注できる仕組みを全体で共有することで持続可能な事業に発展するのだろうと考えられます。

川本園の田中理事長も「うちは県産木材や地域材を使うことをやっていきたい。自分たちで作って自分たちで売ればいいという考え方が変わったことが、このプロジェクトに関わった大きな変化だった。木材を使って多くの福祉作業所の作業になればいい。」と語ります。

ウッドデザイン賞を受賞して
ウッドデザイン賞の応募については、賞設立時から木材関係を盛り上げ、日本の杉を利用していこうという活動がパワープレイスはじめ、メンバー全員にあったからだと言います。
デザインだけでなく、取り組みや仕組みを評価してもらえる賞だからこそ、木材の事を知らない一般の人たちにも知ってもらい認められる。だからこそ、この『森tebaco』も応募する価値があったとプロジェクトメンバー全員が説明します。

「木を使うことで支援者がいた」と田中理事長は受賞の感想として語ります。
「モノより森林組合を入れ、デザイナーさんを入れ、木育ネットさんとも出会えた。社会福祉協議会も入れて一緒に組んだメンバーが良かったからこその受賞だと思います。」
色々な人たちの意見を吸収し、最初はできないと言っていたことが、一年間話し合いをしていく中で職員の意識が変わっていったそうです。利用する障がい者だけでなく、職員も生き生きとしていったことが大きな喜びだったそうです。

各地の事業所とコラボして様々な魅力的な商品を開発することで、福祉施設で働く人たちのやりがいとなる。それが各地の福祉事業所と林業がつながり、地域の木材の活用に繋がる…。
小さく柔らかいぬくもりを手の中で感じる『森tebaco』に秘められた大きなストーリーが2023年度の一等賞と審査員をうならせたのかもしれせん。
現在『森tebaco』はNPO法人木育・木づかいネットの”木づかいショップ”で受注生産にて販売をしています。
⇒NPO法人木育・木づかいネット『日本の森の木づかいショップ』
【参考リンク】